![]() オープンシステムの本
オープンシステムの本
![]()
2001年1月20日発売
「価格の見える家づくり」
〜家づくりの不満を解消していったらオープンシステムになった!
著者:山中省吾/オープンネット(株)代表
出版社:株式会社コスモリバティー社
価格:1500円+消費税
| (巻頭カラー) 「中野邸」住環境・藤田氏 「ホテル・マーレたかた」プルーフ・福留氏 「福島邸」アーキクリエイト・星川氏 「三浦邸」ヴァンクラフト・小杉氏 「安福邸」山中設計・西村氏 第1章 オープンシステム誕生のきっかけ 第2章 走りはじめてみたら ・・・いろんな反応があった 第3章 複雑な仕組みをダイエットしたら 顧客主導の建築革命が起こった 第4章 オープンシステムの財産・設計事 務所のネットワーク 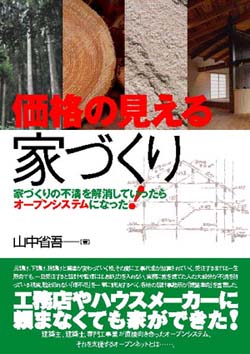 |
第5章 オープンシステムで建てた家 (1色刷りで1件で1ページの写真) ・K邸/幹自然工房 ・吉原邸/カナタニ ・角南邸/カナタニ ・瀬川邸/住まい木創社 ・藤田邸/住環境 ・井口邸/山中設計 ・妹尾邸/山中設計 ・窪山邸/ワード設計 ・井上邸/ワード設計 ・大森邸/アイシー企画 ・上田邸/アイシー企画 ・田口邸/SHOKAN design ・麻野間邸/大村建築設計 ・辻邸/アマ設計 ・子育て支援施設/富士設計 ・小森邸/アーキテック ・竹澤邸/オームラ設計 ・成田邸/南風設計室 ・W邸/現代設計 ・T邸/現代設計 ・長谷川邸/トップ ・みそら野プロジェクト/トップ ・平野邸/ヴァンクラフト ・菊池邸/ヴァンクラフト ・YTCアドレス/大高建築 第6章 建築主の声 第7章 QアンドA 最後に参加設計事務所の連絡先一覧 参加設計事務所宛の質問表 |
注文書
最寄りの書店に在庫がない場合は、この注文書をプリントアウトして書店へお持ちいただきますと、簡単にご注文いただけます。
著者山中氏が執筆後にオープンネット倶楽部に宛てたメール
送信者: "mobile" <mobile@open-net.co.jp>
宛先: <club@open-net.co.jp>
件名 : [club 48] 肩の荷がおりました
日時 : 2000年9月8日 11:05
オープンネット倶楽部の皆様
実は小生、肩の荷がおりてホッとしているところなのです。本の原稿をやっと書き終えたのです。 皆さんには「特別」に「おわりに」だけお届します。本文は秘密です。編集者から3ヶ月後に 店頭に並ぶと言われています。年内ぎりぎりというところでしょうか。印税が入れば (取らぬ狸の皮算用)
「働けど 働けど 我が暮らし・・・じっと手を見る」もいくらか改善されるかなと 思っています。
では・・・。
おわりに
執筆から開放されて、久しぶりに親しい知人を訪問しました。 「山ちゃん、どげしちょった?元気だった?」ずいぶん疎遠になっていたので、 行く先々でからかわれました。やっぱり「外回りのほうが楽しいな」としみじみと 感じた1日でした。例年なら赤とんぼが飛んでいてもおかしくないのに、空にはまだ 夏の太陽がぎらぎらと輝いていました。
案の定執筆は遅れに遅れ、出版社と編集の人たちに迷惑をかけてしまいました。 最初は「すみません。なかなか時間が取れなくて…」と定番の言い訳をしました。 また次の〆切りが近づくと、「設計と同じで、コンセプトが明確にならないと文章は 浮んでこないもんだね」とまるで第三者のような言い訳もしました。でも内心は 「おまえの力不足が一番の原因だよ」と、ちゃんと分かっていたのです。
複雑な建築のことを解り易く表現することにずいぶん苦労しました。 「これ以上深く入り込むとかえって解りにくくなる」と思ったところは、 敢えて説明を省きました。そのため、いくらか誤解を招くような個所もあったと思います。 「それでも良いんだ」と思ってキーボードを打ちました。
何故なら、この本を出す意味は「家をつくりたいと思っているあなた自身が、 専門家と同じ情報を持って、専門家と一緒に結論を出す」ことの大切さを伝えるところに あるからです。専門家だけに結論を委ねていると、誰も気が付かないうちに時として 大きな落とし穴に落ちることもあるのです。だから生活者、そこに住む人、寝る人、 遊ぶ人が参加して結論を出したほうが良いと思うのです。
米子高専建築学科で勉強していたころは、建築の勉強よりも文学や哲学をよく読みました。 経済や組織が優先する世の中に反発も覚えました。時には先生にも反発して、ずいぶん 困らせました。いつしか僕の中で「一人ひとりの人間は何物にも替えることのできない 価値を持つ」という思想が形造られました。建築というフィールドでそれを表現することが、 そのころからのテーマでした。
だから卒業論文のテーマも「建築と人間の関わり」に決めました。当時の私には荷が 重たすぎるテーマだったので未完成に終わりました。それからずっと考え続け、 今やっと卒業論文の続きを書くことができました。「先生、今からでも受け取って くださいますか?」と言っても、卒論担当の宮川久三先生にはもう声は届かないのですよね…。 27年間も経ってしまったのですから。
本当に月並みな表現ですが、「世の中の役に立つ人間になるために勉強をしよう」 と決意しました。「役に立つには本物の人間にならなければならない」ということを毎日自分に言い聞かせてきました。「自分には力が無い。だけどこんな自分でも、いやどんな人間でも無限の可能性がある」と思ったから根気よくがんばることができたと思います。まだ、途上ですけどね。
最後に、青春時代に多くの示唆を与えてくださったフランスのビクトル・ユゴーさんにお礼を言います。ユゴーさんが生まれてからもうすぐ200年ですね…。
2000年8月31日